水の正しい選び方・飲み方健康法
- Japan.De.Aru
- 2017年6月22日
- 読了時間: 6分
宇宙には何百億個の星が存在しますが、私たちが住む地球ほど豊かな水を持ち星は、今現在発見されていません。
水は、気体、液体、個体と姿を変えながら、地球上のあらゆる生命体にエネルギーを供給しています。
京都の鴨川、東京の隅田川、パリのセーヌ川、ロンドンのテムズ川など、古代から綺麗な水が流れる川のある場所に人々は集まって都市を築いてきました。
それは単に飲料水や輸送手段を確保するためだけでなく、水の持ち母性に惹かれて多くの人々が引き寄せられてきたからです。
日本で販売されているミネラルウォーターは、約500種類と言われています。
この水の中から自分に最適な水を選ぶ際、手掛かりとなるのがボトルの裏に書かれている成分表です。
第一に見るべきなのは、水素指数を示すPHと、カルシウム、マグネシウムの含有量を示す硬度です。
硬度100以下は軟水、それ以上は中・硬水です。
サプリメントを飲むときは中性の軟水を、肉の煮込みには硬水を使うのがオススメです。
地層にカルシウムやマグネシウムの成分が多く含まれているほど、そして長く地層に浸透させるほど硬度は高くなります。
ヨーロッパ野水に硬水が多いのは、石灰岩層の地層と、平坦で広大な土地が多いせいです。
長い年月をかけてカルシウムとマグネシウムを多く含む地層を通るため、硬度が高くなるのです。
逆に日本の国土は起伏が激しいため、水の流れも速くなってミネラルを吸収する期間が短くなります。日本に軟水が多いいのはそのためです。
美香氏から日本人は軟水を飲んで生きてきたので、腎臓が硬水をろ過する機能が欧米人に比べて低いのですが、硬水には日本人に不足がちなカルシウムやマグネシウムが豊富に含まれています。
ミネラル豊富な硬水は積極的に体を強化していく水です。
対する軟水は体への負担を掛けずに体内を循環する水と言えるでしょう。
朝と夜は軟水、昼は硬水、疲れたら炭酸水など、時間や状況に応じて変えるのがオススメです。
雪や氷の解けた水は、六員環という特殊な構造をしています。
六員環という水分子は、非常に生理活性が強い。その活性は時間とともに失われ、沸騰や消毒をするとほとんどなくなってしまいます。
良質な水の第一条件は、加熱殺菌されてない事です。加熱殺菌すれば菌はいなくなりますが、水の構造そのものが変わり、美味しさの決めてとなる酸素も炭酸ガスも失われてしまいます。
ミネラルウォーターの四分類
1、ナチュラルウォーター
2、ナチュラルミネラルウォーター
3、ミネラルウォーター
4、ボトルドウォーター
天然水に秘められた抗酸化力を享受するならナチュラルミネラルウォーターに限ります。
中でも、「加熱処理していません」「非加熱ボトリング」などと書かれている生水が、良質な水と言えるでしょう
パワーストーンを水に浸け、暫く置くと、その石のミネラル分を水分子が溶かし込み、ただの水がミネラルを含んだ水になります。トルマリンなどの微弱な電気を発生させる石なら、<br />体内を浄化する作用を持つ水にも変化します。
私たち人間の体は、半分以上が水からできています。筋肉は約75~80%、皮膚は約72%が水分です。水とは無縁に見える骨も、実は三分の一が水分なのです。
人間の体には三種類の水分があります。①血液②細胞の中にある水分③細胞と細胞の間の間質液
体内の水の55%は細胞内にあり、残りの45%は細胞同士の間を埋める細胞間物質の中にあると言われています。細胞の中の水が減ってしまうとナトリウムなどが濃くなって細胞自体が生きていけなくなるので、細胞内の水分はあまり変化しません。
代わりに減るのが、細胞間物質に含まれる水です。この細胞と細胞の間の水分減少こそ、肌の張りを失わせ、皺を作る原因になるのです
成人の場合、男性は約60%、女性は約55%と、女性の方が5%も水分の含有量が少ないです。それは、筋肉より脂肪の方が細胞に取り込まれている水分が少ないからです。筋肉はその75~80%が水分ですが、脂肪は僅か10~30%です。男性よりも女性の方が脂肪が多くて筋肉が少ないため、体内に含まれる水分量も少なくなってしまいます。
水は空腹時が最も効率よく吸収されます。水をこまめに飲んでいると新陳代謝が活発になり、脂肪が燃焼しやすくなります。空腹感は血液中のブドウ糖濃度が低下して、脳の摂食中枢が刺激されるために起こるのですが、この時コップ一杯の水を飲むと、胃液が薄められて胃の中の酸性度が下がり、
脳が満腹だと勘違いします。
つまり、水をこまめに飲む事で、過剰な食欲や間食が抑えられ、肥満予防に繋がるという訳です。
水はすべての生物の大部分を構成し、あらゆる生命活動を支えています。私たちは体内の水分の20%を失うだけで、死んでしまいます。
呼吸の酸素と同様に、水は最も重要な栄養素であり、解毒剤でもあります。
細胞が栄養素を取り込むためにも、有害物質を排泄するためにも、水は必要不可欠です。
綺麗な水を沢山飲んでいると、体内の浄化システムがうまく働いて、有害物質が体内に溜まりにくくなります。
私たち人間の主な臓器の約70%、脳の80%、血液の90%、骨の25%は、水でできています。腎臓、膀胱、腸、肝臓、肺、皮膚などはすべて、毒素や老廃物の排泄に水の力を借りています。また、肺、鼻の内側、喉、気管支、消化器官、目などは常に潤っている必要があるため、水は必要不可欠な存在なのです。血液は90%が水であるために自由に体内を循環し、酸素、栄養素、老廃物などを必要な組織に届ける事ができます。また、細胞内外の浸透圧を一定に保つためにも、発汗によって体温を一定に保つためにも、水は重要な役割をしています。
水を飲むと、胃を通過して、大腸の腸壁から毛細血管に吸収され、毛細血管の壁を通り抜けて、約30秒後には血液へ、1分後に脳と生殖器へ、10分後には皮膚細胞へ、そして、20分後には心臓、肝臓、腎臓へと届きます。水は短時間で全身を駆け巡り、細胞の健康を維持してくれる必要不可欠な存在なのです。
ところが、一日呼吸をするだけで、体内の水分は500ml失われてしまいます。発汗すればさらに大量の水分が失われる事になります。充分に水分が補給されず、脱水症状になれば、筋力の低下、持久力の低下、体温調整機能障害などが起こりやすくなります。最低でも、一日2リットルの水を飲むのが理想的です。
水を飲まないと集中力と記憶力が低下するという研究報告は複数あります。人間の体内から2%の水分が失われるだけで、一気に集中力が低下してしまう事が分かっています。特に夏場の集中力の低下の原因は、暑さ以上に水分不足が影響しています。夏場に水分はこまめに飲んだ方がいいと言われるのは、集中力の持続のためにも理に適っているのです。
水分不足はホルモンの不均衡となって脳にも悪影響を及ぼします。この悪影響を避けるためには、こまめに水分を補給する事です。こまめに水分を補給するだけで、脳の働きを助けて知的能力を向上させる効果があります。
2%の水分の減少を防ぐには、1~2時間にコップ1杯ほどの水分を補給するのが目安となります。
水の働き
体温調節機能
血液の循環促進機能
解毒・希釈作用
鎮静作用
覚醒作用
人間の体の60%は水でできている
脳 75~80%が水
目 90%が水
歯 10%が水
肺 80%が水
心臓77%が水
腎臓80%が水
皮膚70%が水
筋肉75%が水
1960年前後まで、日本の水道水は、世界で有数の水準を誇る良質さで知られていました。しかし、水源の状態はこの50年間で大きく様変わりしています。
浄水器で塩素を取り除いた後の水は殺菌力を失って無防備なので、すぐに飲む事が重要です。








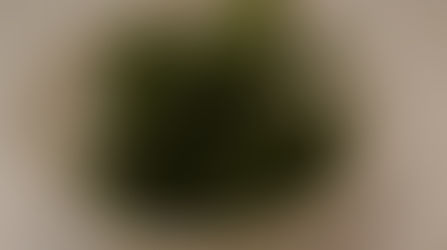


































コメント