不食という生き方
- Japan.De.Aru
- 2017年6月25日
- 読了時間: 8分
"不食"
地球上に存在する生物は、大きく二種類に分ける事ができます。
それは、独立栄養生物と従属栄養生物です。植物は独立栄養生物に属し、動物は従属栄養生物に属します。ところが、地球上には独立栄養生物に属する人間が存在するのです。
何も食べないで生きている人は、現在でも世界で10人ほど確認されています。彼らは、空気と水と太陽の光だけで生きているのです。不食に至るまでの過程として、ヴェジタリアン⇒フルータリアン⇒リキッダリアン⇒ブレサリアンという段階があります。不食になるためにはまず、動物性食品の摂取を止めて菜食主義者になる事から始まります。肉を止めて、魚を止めて、卵を止めて、乳製品を止めて、穀物を止めて、最後は野菜と果物だけで生活し、そして、食べる量を少しずつ減らしながら、やがては菜食すらも止めるという形で行われます。しかし、不食によって体が痩ほとんど食べなくても痩せないそうです。体調も良くなって、疲れにくくなりますし、病気にもなりません。不食になると食べ物を消化するエネルギーを使わなくなるので、睡眠時間も短くて済みます。現在、日本には青汁だけで生活している人が20人ほどいるそうです。以前、『歴史ミステリー』という番組で、明治時代の不食者を取り上げていました。その不食者は、長南年恵さんという女性で、20歳の頃から全く食事を摂らず、24年間、口にするものは生水程度であったと言われています。長南年恵さんは43歳で亡くなるまで、10代の少女のような容姿を保っていました。不食こそが不老への最高の近道だと言えます。人間の基礎代謝は1300kcalです。
そのうち脳が使うのが500kcalであり、意識不明でも500kcalは必要なので、
1日の総摂取カロリーが500kcal以下の人を仙人と呼びます。
長期間、不食を継続すると呼吸が一分間に二回と深くなります。呼吸が二分間に三回より深くなると完全な瞑想状態になります。血中酸素濃度は低くなり、心拍数、脈拍数も遅くなります。脳波もアルファ波やシータ波にまで下がります。地球上に存在するあらゆる生物の生命維持エネルギーの源は太陽光線です。植物は光合成によって太陽光線をエネルギーに変換して体内に蓄積しています。動物は、植物を食べる事によって太陽エネルギーを間接的に体内に取り入れています。直接、間接を別にすれば、生物は葉緑素の働きを通じて、生命を維持している訳です。しかし、植物という媒体を通さずに、太陽光線のエネルギーを直接吸収する事もできます。日の出間際と日没間際の太陽を一時間凝視する習慣をつけると食欲が湧かなくなるのです。
太陽凝視以外の方法として考えられるのが、ブルーソーラーウォーターです。ブルーソーラーウォーターを飲むと、お腹が空かなくなり、全く疲れなくなります。ブルーソーラーウォーターの作り方は、水道水かミネラルウォーターを青色の硝子瓶に入れ、プラスチック栓かサランラップか青色のセロファンで蓋をし、太陽光に一時間当てるだけです。ブルーソーラーウォーターは、ペットボトルに移して冷蔵庫に保管する事もできます。不思議な事に、水が甘くて美味しくなります。蓋は必ず非金属でなければなりません。活動エネルギーを生み出すには、電子伝達系という回路で、一個の陽子と一個の電子で成り立っている安定した分子構造の水素を栄養素から引き離し、ミトコンドリアの膜の内側と外側に電位差を作らなければなりません。実は、この水素分子を引き離す仕事を太陽光線が行っているのです。栄養素を口から摂取するだけでは、充分なエネルギーを生み出す事ができません。太陽の光を浴びると、体が温まり心地よく感じられるのは、ミトコンドリアが刺激され、活性化するからです。ミトコンドリアを中心として栄養学を捉え直した場合、食べ物だけではなく、太陽光線も栄養の一部なのだと言えるのです。主なエネルギー源は糖質ですが、糖質は解糖系で分解されるとピルビン酸と乳酸になります。
この際に生み出される活動エネルギーはわずかなので、ピルビン酸はミトコンドリアに運ばれ、電磁波や放射線のエネルギーも加味されながら、最終的に大量の活動エネルギーが作られます。食べ物以外の要素がいくつも加わり、最後は燃焼とは別の形で活動エネルギーが得られます。カロリー計算で成り立っている現代栄養学との間に大きな食い違いが生じるのも当然です。
不食になるためには解糖系からミトコンドリア系へとシフトする必要があります。ブドウ糖が細胞の中に入って来ると、細胞質では解糖という反応が起こります。効率の悪い解糖系エネルギーを活用するには、絶えず糖質を取り込む必要があるため、糖が不足してしまう時間が続くとすぐに空腹になり、猛烈な飢餓感に襲われます。
エネルギー効率のいいミトコンドリア系の世界に入り込む事ができれば、飢餓にも適応できます。解糖系の世界から離脱するのに最も有効な手段は断食と断糖です。断糖とは、今、医療現場で注目されつつある糖質制限食を意味します。断食が食事そのものを断つ事で解糖系を縮小させるのに対し、糖質制限食では主なエネルギー源である糖質のみを対象にして、これを断つ事でミトコンドリア系を活性化させる訳です。
解糖系は糖質をエネルギー源にしていますから、糖質を遮断すれば解糖系は自然に縮小するのです。修験僧が五穀断ちをするのは、糖質制限食によって解糖系の欲の世界から解脱し、ミトコンドリア系優位の悟りの世界へとシフトチェンジするための知恵なのでしょう。
植物は葉緑素により、太陽エネルギーを物質化し、自らを生長させます。動物は生命小体により、太陽エネルギーを物質化し、自らを成長させます。通常、動物の生命活動は食物を摂る事で、その熱エネルギーと物質変換が営まれます。しかし、それだけでなく緊急避難時のバックアップ・システムが準備されています。それが、解糖系エネルギーや核エネルギーによる補助システムです。最後には不食、飢餓に備えて究極の生存システムが人体に備わっています。それが、太陽光によるソマチッド造血です。
普段、食物から充分にエネルギーを摂っている時は、このシステムは作動しませんが、不食、飢餓状態になって初めてこの緊急バックアップ・システムは作動するのです。肥満と関係が深いいくつかの遺伝子のうち、ベータ3アドレナリン受容体遺伝子というものに変異があると、中性脂肪の分解が抑制され、基礎代謝量が低くなります。この遺伝子変異は、ネイティヴ・アメリカンのピマ族に多い事が知られています。ピマ族は、10人に9人がこの倹約遺伝子を持っているそうです。実は、ピマ族ほどではありませんが、この倹約遺伝子は日本人にも多く、約3人に1人が持つと言われています。民族的に見ると、倹約遺伝子を多く保有している民族は、イヌイット、ピマインディアン、日本人の順だそうです。日本人は欧米人と比較してインスリンの分泌能が半分程度で、欧米人より倹約遺伝子を多く持っているという報告があります。日本で農耕が始まったのがヨーロッパに比べてかなり遅れたためかもしれません。
倹約遺伝子の持ち主は、そうでない人と比べて基礎代謝量が1日200~300kcalも少なくなります。倹約遺伝子を持っているかどうかは糖質制限食を開始して最初の1週間で分かります。この間に体重が減らなかったら倹約遺伝子を持っていると推定できます。倹約遺伝子を持っている人ほど飢餓には強く、不食に向いていると言えます。不食に対して多くの人が抱く第一の疑問は、体の蛋白質をどうやって作っているのかという事でしょう。その答えは、腸内細菌です。不食者の腸内細菌の種類や割合は、人間としてはかなり特殊で、牛などの草食動物に近いそうです。不食者は牛などの草食動物と同様に、消化管の中にバクテリアが棲んでおり、セルロースを分解してアミノ酸を合成できるのです。では、アミノ酸の材料となるアンモニアは、どこから調達しているのでしょうか。私たちの体では、筋肉などの蛋白質が絶えず代謝されています。少しずつ古いものを捨てては新しいものを作っているのです。要らなくなった筋肉の蛋白質を分解する時、代謝産物としてアンモニアが生じます。アンモニアは有害なので、体内では尿素に変えられ、主に尿として排泄されます。こうして捨てられるアンモニアや尿素には、実はたんぱく質の材料になる窒素がまだかなり含まれています。不食者は、その窒素を捨てずに再利用しているというのです。 太古の昔から、私たち人間を含めたあらゆる動物が最も恐れていたのは、外敵ではなく飢餓でした。人類最古の生活様式である採集狩猟をしていた頃は、食事の時間も回数も一定していませんでした。獲物が捕まえられなければ数日、時には数週間も空腹で過ごさなければならなかったのです。人類の長い歴史を振り返ると、ほとんどが飢餓にさらされている時代であり、人類は、少ない食糧を効率よくエネルギーに変えながら淘汰、進化してきた訳です。人類は、食べた物を内臓脂肪として効果的・効率的に蓄積する事ができる倹約遺伝子と断続的な飢餓状態に置かれた時に体を生き延びさせてくれる延命遺伝子を持っています。私たち人類が飢餓状態になると、体は老廃物を無駄に捨てるのをやめてしまいます。無駄に出す事をやめて、マクロファージが再利用し、一つの無駄もなく再利用して、あとは消化管に棲みついた腸内細菌を栄養にして、不足分を賄って生き続けるのです。
人間の四段階のエネルギー供給システム
第一段階
酸化エネルギー系 カロリー理論の根拠
第二段階
解糖エネルギー系 酸素不要
第三段階
核エネルギー系 元素転換
第四段階
太陽エネルギー系 生命小体ソマチット








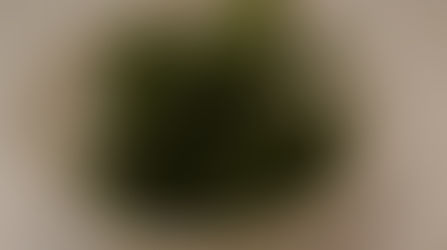


































コメント