特集
- Japan.De.Aru.
- 2019年2月19日
- 読了時間: 3分

日本、オランダ、ついにアメリカも 培養肉の時代がやって来る
<米農務省も監督に乗り出すと発表。牛も豚も鶏も殺さない「人工肉」がいよいよ本格化へ>
「動物なしに肉を育てられるなら、そうすべきではないか」
SF作家やアメリカ動物愛護協会の問い掛けではない。米食肉最大手タイソン・フーズのトム・ヘイズ前CEOが昨年9月の退任の少し前に述べた言葉だ。
タイソンといえば「チキン」と同義と言えるほどのブランド。そのCEOがなぜ食肉生産から動物をなくしたいと考えるのか。
1つには、そうすればもっと効率的に食肉生産ができるから。骨や羽、毛のない肉を生育すれば同じ費用や時間で、より多くの肉が手に入る。
国連食糧農業機関(FAO)は、動物を育てて殺し、食料にすることは「地球温暖化、土地劣化、大気・水質汚染、生物多様性の喪失など、世界的な喫緊の環境問題の主な原因になっている」と指摘する。
2017年に動物の権利擁護シンクタンクが行った調査によれば、70%近くの人が今の食料システムにおける動物の扱われ方に何らかの不快感を覚え、半分近くの人が食肉処理の禁止を支持している。この潮流を確認するためオクラホマ州立大学が行った追加調査でも、同じような結果が出た。
幸い、ヘイズが言うような畜産も食肉処理もなく肉を食べられる世界は現実になりつつある。動物の細胞を培養して作る肉に世界中の企業が取り組み、生産コストも下がりつつある。醸造所のような施設内で育てられたクリーンミートと呼ばれる「細胞ベース」の製品は、私たちがいま食べている肉にDNAまでそっくり。しかも、糞便汚染や抗生物質の慢性使用とも無縁だ。

食肉輸出国でいるために
これだけの利点があるのだから、「そうすべきではないか」という問いに反論するのはますます難しくなっている。従来の食肉に対してコスト競争力を持てるよう生産を増やすという課題はあるが、食卓に上げるための大きな科学的進歩は必要ない。
現在の主な問題は、どの国がリードしていくかだ。日本やオランダ、イスラエルの政府は既に研究や新規事業へ投資している。培養肉が対処の一助となれる世界的問題の大きさを考えれば、これらの国々の努力は称賛に価する。
しかしアメリカにとっても人ごとではない。米農務省の推計では、アメリカ人の1人当たりの年間食肉消費量は、昨年は100キロ以上と過去最高になった。
米政府も培養肉開発の第一線にいたいと考えているようだ。米国科学アカデミー(NAS)はホワイトハウスへの報告書の中で、特に成長が期待される技術として培養肉を上げた。ソニー・パーデュー農務長官は、アメリカが主な食肉輸出国であり続けるには、細胞培養肉が重要だと指摘している。「どうしたらもっと効率よく食肉を人々に提供できるか、われわれは考えるべきではないか」と、彼は語った。「これらの技術を積極的に利用する必要がある」
そして昨年11月には米食品医薬品局(FDA)と米農務省が、ついにクリーンミートの生産を共同監督する計画を正式発表。これはメンフィス・ミーツやジャストといったアメリカの培養肉トップ企業にとって、市場に正々堂々と入っていけるという明確なメッセージとなった。
時代は、牛も豚も鶏も不要の食肉へと向かっている。








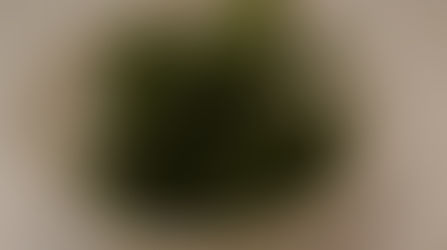


































コメント